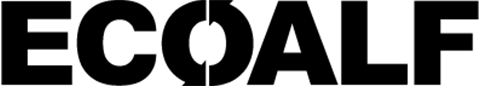COLLABORATION
アルミ×ファッション
Part1 サステナビリティファッションブランド「ECOALF」創業者へ聞く、
“環境を良くする服”ってなんですか?
Part1 サステナビリティファッションブランド「ECOALF」創業者へ聞く、
“環境を良くする服”ってなんですか?

Featuring
ECOALF President/Founder
ハビエル・ゴジェネーチェさん
ハビエル・ゴジェネーチェさん

Interviewer
UACJ 牛山 俊男

Interviewer
UACJ 大坪 由佳
Because there is no planet B®(第2の地球はないのだから)。そんな力強いメッセージを掲げるサステナブルファッションブランド「ECOALF(エコアルフ)」。海洋ゴミや廃棄素材を服に生まれ変わらせる取り組みで、世界中から注目を集めています。今回、UACJは新たなプロジェクトとしてECOALFの店舗什器であるアルミ素材を使用した「シューズタワー」を制作。第一弾では、ECOALF創業者のハビエル・ゴジェネーチさんにサステナブルファッションについてのお話を。そして第二弾では、同ブランドの日本展開を担う三陽商会と共に、コラボレーション制作の舞台裏を。2つのインタビューをお届けします。


2025年9月12日に高輪ゲートウェイ駅に開業した「ニュウマン高輪」。世界各国の最先端ブランドが集結するその一角にある「ECOALF」にやってきたUACJの牛山と大坪。グランドオープンのため来日中の創業者ハビエル氏へ、早速お話を伺います。

ブランド誕生の
きっかけは?
きっかけは?

ハビエル
はじまりは、ブランド名の由来にもなっている息子のアルフレッド、アルバロの誕生でした。「息子たちの未来に何を残せるんだろう?」という考えをきっかけに、2009年ECOALFを創業しました。

大坪
そこからファッションのあり方を見直す方向に?

ハビエル
そうですね。当時からファッション業界がかかえる環境問題に対して何かできないかとずっと考えていました。

大坪
ファッション業界は環境に負荷をかけている産業の一つであるということはよく知られています。

ハビエル
つい先週もガーナに現地取材に行ったんですが、そこで見た光景は本当にショッキングなものでした。ファストファッションのゴミの山がそびえたっていて、毎週1500万トンものゴミがヨーロッパから運ばれてくるそうです。

大坪
1500万トン!ちょっと想像ができない量です…。

ハビエル
ファッションは美しいものですが、一方で、私たちは大量に生産し、大量に廃棄することを繰り返している。今こそ、この問題に真剣に向き合い、作り方や、私達の生き方そのものを変えていかなければ未来の地球はありません。


リサイクルから生まれる
ファッションとは?
ファッションとは?

ハビエル
ECOALFでは“すべてのアイテム”をリサイクル素材や環境負荷の低い天然素材のみで作っています。

牛山
“すべてのアイテム”というのがすごいです。例えば、どんな素材があるんでしょうか。

ハビエル
不要になった漁網やカーペット、ナイロン廃棄物を回収してつくられたリサイクルナイロン。廃タイヤやコーヒー豆のかすまで、いろんな素材を使用しています。

牛山
廃棄となるはずだったものが、素材としてまた生まれ変わる。素晴らしい循環ですね。素材の調達はどのような仕組みなんでしょうか?

ハビエル
私たちはECOALF財団という団体を運営しています。そこを通じて、さまざまな環境活動への支援を行い、その中で、材料となる廃棄物も一部調達しています。

牛山
なるほど!その一つが「Upcycling the Oceans」ですね?

ハビエル
はい。「Upcycling the Oceans」は2015年からスペインの漁師たちと始まった、海底に沈んだプラスチックゴミを引き上げるプロジェクトです。

大坪
漁師さんと連携するファッションブランドなんて、聞いたことがありません。

ハビエル
実は海のゴミの75%は、海面ではなく海底に眠っているんです。漁をする際に、漁師が釣り上げたゴミを持ち帰ってもらい、分別・再生して繊維に変えているんです。

大坪
海をきれいにしながら、衣類を作る。服を作ることが環境保全や改善につながるというのは新しい発想です!

リサイクルマテリアルやアップサイクルマテリアルから作られているECOALFのスニーカー。驚くほど軽く、履き心地も良い。廃棄物というネガティブさを感じさせないスタリッシュなデザイン性も特徴。
どうやって
ファッションから
環境を変えていく?
ファッションから
環境を変えていく?

ハビエル
ファッションのサステナビリティと聞くと、リサイクルされた素材がまず頭に浮かぶと思うんですが、実はそれだけではないんです。

牛山
どういうことでしょう?

ハビエル
どう作って、どう届けて、またどうプロモーションしていくのか。そのすべてがファッションから環境を変えていくことにつながっています。

牛山
ということは、作る過程にも工夫があると。

ハビエル
はい。プロダクトを作る過程において電気や水などの資源を削減する作り方へと変えることで、環境へのインパクトを減らしています。

大坪
それが、環境負荷の低い素材ということですね。

ハビエル
リサイクル素材も資源使用量の削減に有効です。例えば、リサイクルコットンはTシャツ1枚あたり通常のコットンでつくるよりも2500リットルの水を節約できます。

牛山
数字にするとその効果がよりわかります。

ハビエル
それから店舗でできることもたくさんあります。店舗全体をブランドのメッセージを伝える舞台として、内装や什器、そこでできる体験、発信する情報も含めて、サステナビリティを感じられる場と捉えています。

大坪
ここ、ニュウマン高輪店でもそういった取り組みはされているんでしょうか。

ハビエル
「simplicity(シンプリシティ)」というコンセプトのもと、壁や床、什器には漆喰や廃材木材などを使って、極力少ない材料で日本らしいシンプルでミニマルな空間を表現しています。

大坪
店舗もサステナビリティ発信の場にする、という考えはおもしろいですね。

ハビエル
私が店づくりで重視しているのは、その国や土地の風土を取り入れた店舗づくりをするということ。その場所の文化やアイデンティティーを尊重して、その土地の人にとって馴染みやすく、親しみやすい事は、サステナビリティを身近に感じてもらう一歩として有効ですから。

大坪
とても柔軟な考えですね。勉強になります。

回収プロジェクトによって集められたペットボトルを活用したマネキンのインスタレーション。高輪ゲートウェイ駅からも見える立地を活かし、ブランドメッセージを発信している。



「環境によい」と
「おしゃれ」は
両立できる?
「おしゃれ」は
両立できる?

ハビエル
難しいけれども私はできると思っています。ECOALFはミッションとして、 「リサイクルされていない製品と同等の品質・デザインの製品をつくる」ということを掲げていますから。

牛山
サステナブルだけど、ファッション性もしっかりと重視するということですよね。

ハビエル
その通り。 ファッションブランドなので、見た目の美しさや、着たい服であることは大事にしています。


大坪
その視点は、サステナビリティに対するイメージをアップデートしていく上でも大事ですよね。

ハビエル
2009年の創業当時はリサイクル、サステナビリティというのは“クールじゃない”と言われ、どちらかというとネガティブなイメージでした。例えるなら、おばあちゃんの古いブランケットをもらって、それを使って何かを作るようなイメージです。
でも、私がやりたかったのは、リメイクじゃなく、素材からちゃんとしたものづくりです。廃棄物(ゴミ)を循環ポリマーにして、糸にして、そして生地に仕立てて、服にする。
でも、私がやりたかったのは、リメイクじゃなく、素材からちゃんとしたものづくりです。廃棄物(ゴミ)を循環ポリマーにして、糸にして、そして生地に仕立てて、服にする。

大坪
素材から作るということは、相当な苦労があったと思うのですが。

ハビエル
最初の数年は本当に大変でした。素材を探す・開発するところからだったので、2009年に創業はしましたが、実際にコレクションをスタートしたのは2013年。時間をかけて信じて進んできて、それが今やっと実を結んでいます。

大坪
私たちUACJもリサイクルアルミを活用したブランド「ALmitas⁺ SMART」を打ち出しているのですが、今のお話は大変励みになります!信じて、地道に取り組み続けていくしかないですね。

牛山
ECOALFのデザインを一言で表すとなんでしょう。

ハビエル
タイムレスデザイン。時代が変わっても飽きのこない普遍性と品質、長く愛されるデザインを目指しています。

牛山
普遍的な価値をプロダクトでも表現していく、これもまたサステナビリティですね!

PREVIEW FALL/WINTER'25 NEW COLLECTION/83種類のマテリアルを使っている。
マーケットとしての日本、
どう見ている?
どう見ている?

ハビエル
私は世界の中で、日本は大切なマーケットの一つだと位置付けてます。

牛山
その理由はなんでしょうか。

ハビエル
欧州に比べれば日本はまだ「サステナブルファッション」が浸透していない。だからこそ、これからの拡大に期待ができると感じるんです。

牛山
ハビエルさんがおっしゃる通り、日本ではまだサステナブルファッションやその意識さえも浸透しきれていない状況ですね。

ハビエル
正直に言うと、私はショックなんです。「日本はサステナビリティが遅れている、重要視していない」という意見を耳にしますが、本来日本は伝統や文化、自然を大切にしている国という印象を持っています。じゃあなぜそこがサステナビリティに結びつかないのかなと。

牛山
私たちもアルミを扱っていると、欧州では“よりサステナブルな素材だから”という理由でアルミニウムボトルを選択してもらうことはよくあるんですが、日本は全く違う。意識の差を感じますね。

ハビエル
これからもっとサステナビリティと向き合って欲しいですし、日本はそれができる国だと信じています。

牛山
「Because there is no planet B ®(第2の地球はないのだから)」ですからね!



日本限定コレクション「ACT」も展開。店舗コンセプトだけでなく、プロダクトにおいてもその国の文化やアイデンティティーを取り入れていくというハビエル氏の思想が反映されている。


アルミについての
印象を教えて!
印象を教えて!

ハビエル
アルミニウムは半永久的に使い続けられる、循環性に優れた素材だということは理解しているので、とても可能性を感じています。

牛山
もしもハビエルさんがアルミで何か作るとしたら、何を作りますか?

ハビエル
アクセサリー。あとは、アルミだけでできた店舗を日本に作ってみたいです。

牛山
今回私たちUACJは新たなサステナブル什器として、アルミのシューズタワー制作に一緒に取り組ませてもらいました。

ハビエル
アルミ什器も今後もっと増えていくといいですね。新しい取り組みに、私も期待しています。

牛山
2025年10月8日からは新宿伊勢丹でもPOP UPイベントを開催されますよね?新しいアルミ製の什器も提供させていただく予定ですので、私たちもとても楽しみです。ちなみに、今回ノベルティとしてアルミ箸も起用していただきましたけど、ハビエルさんのご感想は?

ハビエル
これはいいですね!こういう日本らしいものがあるのはとてもいい。私も早く使ってみたいです。


未来は
どう変わっていく?
どう変わっていく?

ハビエル
難しい質問ですね。新しい技術や新しい素材は日々生まれている。私はブランドをはじめてから、やればやるほどやりたいことがどんどん増えていく、という状態なんです。

大坪
それだけ技術も意識もアップデートされている、ということですね。

ハビエル
創業した2009年当初はサステナブルな素材というものはなかった。それがこの20年弱の間にサステナブルな素材が生まれ、拡がり、今では683の素材を使ってプロダクト作りをしています。だから、いつも自問しているんです、これはベストか?もっとできることは?って。

大坪
常に探求されているんですね。将来、想像もできないような素材で服が作られているかもしれないと思うと、ワクワクします。

牛山
私たちもアルミニウムという素材を使って、少しでもサステナビリティに対する意識やより良い環境を作れたらと今日改めて強く感じました。頑張ります!

ハビエル
一緒に頑張っていきましょう。未来の地球のために。ありがとう!

牛山

大坪
ありがとうございました。
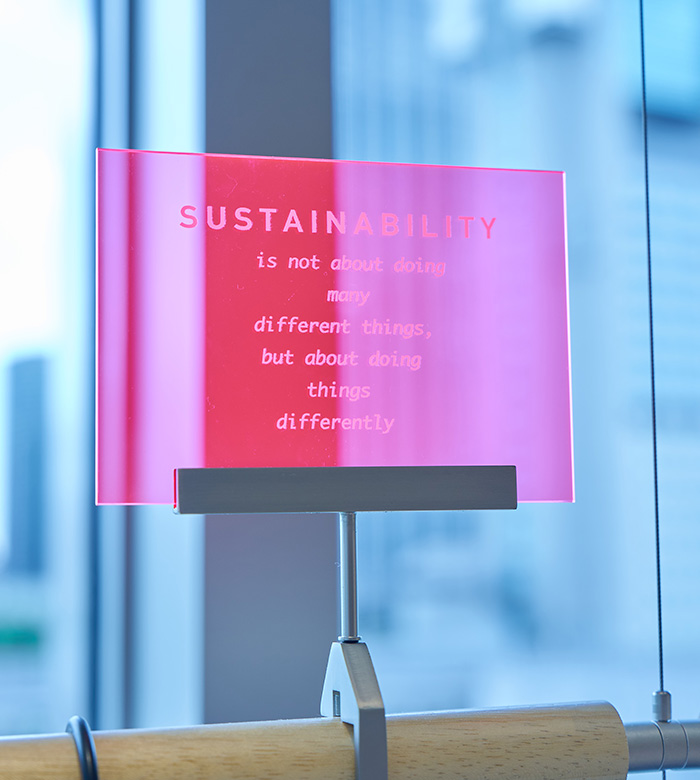



AFTER INTERVIEW

UACJ 牛山 俊男
「タイムレスなデザイン」という言葉には衝撃を受けました。サステナビリティを表現する手段に、リサイクル素材を活用すること以外の方法があることが驚きでした。自身の思い描く世界感を実現すべく、素材まで立ち返る姿勢に、素材の持つ力を改めて感じることができました。未来の地球のために、アルミニウムができることを体現していきたいです。
Profile
マーケティング部で、未来の市場を開拓すべく、業界を問わず、さまざまな人との“軽やかな“繋がりを創造中。

UACJ 大坪 由佳
「日本は自然、伝統、文化とサステナブルなものがたくさんあるのに、なぜサステナブルではないと言うのか」というハビエルさんの言葉に、ハッとさせられました。着物など時代に適した形で継承されているものは今もあります。ただ、私たち自身がそれを少し忘れてしまっているかもしれない。日本らしいサステナブルな社会のあり方を、共創の中で一緒に探していきたいなと、まさにSDGs17を強く実感しました。
Profile
「マテリアリティ総括部」で活動しています。環境負荷の低い食材、洗剤、化粧品を選ぶ、リフィルステーションを利用するなど、不便なところも楽しみながら小さなMyサステナビリティを続けてます!
ECOALF POP UP EVENT
日時:2025年10月8日〜14日
場所:新宿伊勢丹2F
イベントURL
https://store.sanyo-shokai.co.jp/blogs/news/ea-isetanshinjuku-251008
場所:新宿伊勢丹2F
イベントURL
https://store.sanyo-shokai.co.jp/blogs/news/ea-isetanshinjuku-251008
※こちらのイベントは終了しました
NEXT
第二弾インタビュー
次回、ECOALFと、UACJの環境配慮型ブランド「ALmitas⁺ SMART」によるコラボレーションをご紹介。UACJ初となるアパレル業界との取り組み “再生アルミ什器”について、シューズタワー開発秘話をプロジェクトに関わったUACJメンバーと三陽商会(エコアルフ ジャパン)下川さんへのインタビューをお届けします。
※こちらに掲載している情報は取材当時のものです